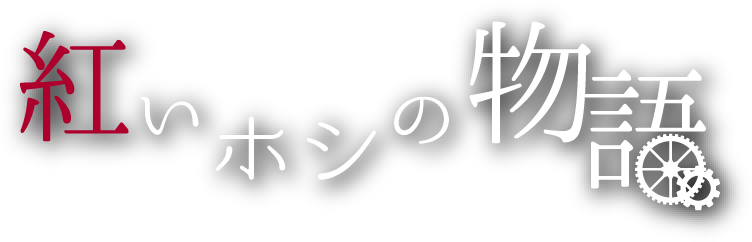星降 ノ華簪
2
天まで続く何本もの軌道エレヴェエタの合間を見え隠れする淡い月は、薄暗くなり始めた空に空いた穴のようでもある。
外つ国では、満月の夜に魔物が蔓延ると言われている。そんな話をしていたのは誰だったろうか、と、和は湯屋の帰り道に現れ始めた月を見上げて頭を巡らせた。
或いは、何かの本で読んだのかも知れない。杜京にある色街の遊女は大体が地上の出身であり、和も例に漏れずその一人である。昔の友人は地上では珍しい本屋を営んでいて、和はよくそこに入り浸ってはぱらぱらと本を捲っていたものだった。
女衒屋に見込まれて杜京に来てからは、その友人とも会えなくなった。しばらくは郵便でやり取りしていたものの、なんとなく返信が滞って久しい。その代わりに、足繁く通い詰める客への手紙をしたためるようになった。
そうして、少しずつ色街の女になってゆく。その事に特に感慨は無いし、昔を懐かしむ気持ちがある訳でもない。ただ、胸にわだかまる空虚さは、どんなに享楽の日々を過ごしても拭える事はなかった。
ふう、と小さく息を吐いて、怪しく光り始めた提灯の灯りの中を歩き続ける。湯上がりで浴衣を簡単に巻き付けただけの体に、吹き抜ける風が心地良い。天の河の祭りが近いからかあちこちに立てられた笹は、その葉と吊るされた七夕飾りをゆらゆらと揺らす。完全に暗くなる前に妓楼へ戻らなくてはならない。しかし、和の足取りは心なしか重かった。
ふと、色街のあちこちで焚かれる香の匂いに混じって、奇妙な匂いが和の鼻腔をくすぐった。夕餉の匂いかとも思ったが、どうにも嫌な感じがする。
和は周囲を見回すと、店と店の間に小さな路地があるのを見つけた。覗き込むとその奥に、こぢんまりとした鳥居が佇んでいるのが見えた。はて、こんなところに神社などあっただろうかと歩み寄ると、妙な匂いが更に濃くなったように感じた。
「ふむ」
こめかみのあたりに滲む汗を首にかけた手拭いで拭き取ると、和は静かに鳥居へと歩みを進めた。管理がされているとは思えないその鳥居は、殆ど色が剥げて剥き出しの木肌のあちこちに朱色の塗装を残すだけだった。
いつの間にか風も止んでいた。周りを建物や雑木林に囲まれているせいか。不快な生温さが和を包んでいる。重い空気の中を、和はゆっくりと歩いていった。
「……!」
小さな社の前にその男は居た。日本刀を片手に持ち、赤黒い血に塗れた姿は、それだけで唯ならぬ威圧感を放っている。月を見上げていたその眼がゆっくりと、和の方に向けられた。その眼光は鋭く、澱んだ暗い紅色をしていた。
「……紅(くれない)」
そう呟いた和の言葉に、男は少し目を細めた。巷を騒がせる赤髪赤目の殺人鬼が、確かそんな通り名であったと記憶していた。まるで外つ国の魔物のように、満月の夜にだけ現れて凄惨な姿となった遺体だけを残してゆく。そのせいで、満月の日はめっきり客が寄り付かなくなってしまったのだ。
男は和に歩み寄り、手にしていた日本刀をその首元に突き付けた。
「誰だ、お前は」
「……ただのしがない女郎さ」
「そうか。運が悪かったな」
「殺すのかい?」
「そうだな」
つぷ、と、刃先が皮を切り裂いたのがわかった。和は真っ直ぐ男の目を見据えていた。その瞳よりももう少し暗い紅色をした髪は無造作にまとめられている。自分を殺そうとしている相手を前にしておかしな話だが、その瞳も髪の色も美しいと和は思っていた。まるで、先日簪屋から買った紅いホシのような色だ。
どれぐらいそうして見つめ合っていたのだろう。男の手は、止まったままだった。
「どうしたんだい?」
「変な奴だ。怖がりも、命乞いもしない」
男の言葉に、なぜだか和はふっと笑みが溢れた。
「そうだねぇ……地上上がりの女郎なんて、その辺で打ち捨てられててもおかしくないだろう? あんたみたいな綺麗な男に、ひと思いに貫かれるのも、悪かぁないと思ってさ」
そう言って、和は男の刃にそっと触れた。その首からは少しずつ、血が滲み出している。和は指先を首元に当てて、その血を拭い取った。そしてその血を口元に寄せて、唇につう、と色をつけてみせた。
刹那、男の刃が首から離れて、その紅い瞳が間近に迫っていた。唇を押し当てられた、と気付いたのは数秒後。気付くと男は和の背に腕を回し、唇を貪っていた。
「んっ……うぅ……」
互いの唇の端から漏れ出る吐息。先程切られた首の傷が熱い。口の中に充満する鉄臭さを感じた時、先程感じた妙な匂いが血の匂いであったことに和は気付いた。
からん、と何かが落ちる音がした。同時に、和のまとめ髪がばさりと解け落ちる。和の何もかもを貪り尽くしそうな勢いだった男の動きが止まった。目を向けると、落ちていたのは先日簪屋から買い求めた紅いホシの簪だった。
「あ……」
先に簪を手に取ったのは男だった。その紅い色は、まるで男の眼と共鳴するようにゆるゆると鈍く輝いていた。
「これを、どこで?」
「……馴染みの、簪屋さ」
男の興味が簪に移ったことに、和はやや不快だった。しかし男は和の心中など察する事なく、簪を眺めている。
「紅い天隕石……」
男はそう呟くと、簪を握りしめる。
「その簪が、何か」
和が全て言い終わらないうちに、男はまた和に近付いて、今度はその首元を舐め上げた。
「んぅッ……」
「次の満月の夜、またここで」
男は和にそう囁くと、簪を握ったまま忽然と何処かへ走り去ってしまった。和は緊張の糸が切れたように、その場に座り込んだ。辺りに残る血生臭さに、体の芯が熱くなる。
こんな、こんなことがあるだろうか。地上にいた時も、杜京に来てからも、こんな感情を抱えた事はない。わなわなと震える指で、切られた傷をそっとなぞる。傷の痛みと熱さが、今の出来事が幻ではないと確信させた。
「天隕石……?」
和がやっと絞り出した言葉は、男が簪を見て呟いていた、あの言葉だった。
終
- ≪前へ
- 紅いホシの物語 TOP
- 次へ≫