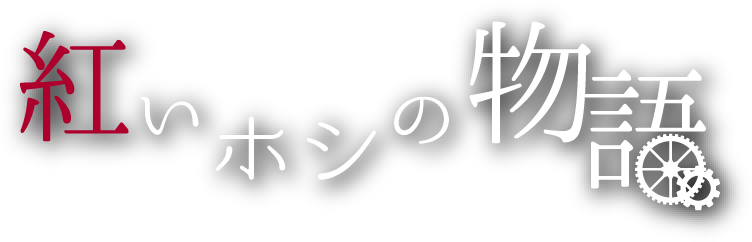星降 ノ砂簪
2
「しかし、採集できるのが十六夜の月の頃とはな」
そう言って、衣琉は軌道エレヴェエタ越しに月を見上げた。ともあれば満月に見える月だが、よく見るとやや欠けているのがわかる。
「ううぅ……ほぼ満月じゃないですか。あの殺人鬼が出たらどうするんですか……」
「紅(くれない)の事か?」
「そうですよ! 満月の夜に現れるっていうじゃ無いですか!」
「それなら、心配要りませんよ」
衣琉に食ってかかる助手に声を掛けたのは、件の簪屋であった。助手は突然声を掛けられてしばし呆気にとられていたが、慌てて衣琉の隣に居直った。
「やあ、貴女が助手君の話していた簪屋ですね! お噂はかねがね! ワタクシ、今回同行させていただきます杜京国立研究所地上調査局の衣琉と申します!」
「初めまして……でも無いですね。地上調査局には一度、軌道エレヴェエタ付近での活動の許可を取りに行った事があります。恐らくその時にお会いしてるかと」
「なんと! それは申し訳ない!」
からからと笑う衣琉を横目に、助手はおずおずと簪屋に声を掛けた。
「あの……心配無い、というのは?」
「ああ、紅の事でしょう? これまでも十六夜の時にこうしてホシを獲りに出ていますが、何故か一度も出くわしたことは無いんですよ。確かに昨日も紅の被害報告は出ているみたいですが、被害者の方には申し訳ないんですけどそれだと逆に安心なんです。これまで満月の翌日に、奴の被害が出た事はありませんからね。恐らく奴は厳密に、満月の日にだけ活動しているのでしょう」
「ふぅん、律儀な奴なんだな。あ、いや。殺人鬼に律儀というのも変な話か」
「まあ、相手は殺人鬼なので、いつルールを変えてくるかはわかりませんがね。ホシの希少性もありますが、そういった危険性も孕んでいるので、簪はそれを鑑みた値段にさせて頂いています」
そう言いながら、簪屋は軌道エレヴェエタに歩み寄った。軌道エレヴェエタ周辺は、その本体を過去に支えていたであろう鉄筋などが朽ち果て、その錆で一面赤黒く湿っている。簪屋は突然立ち止まって座り込むと、その湿った錆砂の中から何かを取り出した。
「ほら、これがホシですよ」
すかさず、衣琉と助手は簪屋の手の中を覗き込んだ。ごつごつした小さなその石は、ぱっと見には他の石と見分けがつかない。しかし、衣琉が携帯していた洋燈で照らしてやると、煤けて炭化した表面の一部が割れていて、その中が仄白く煌めいているのがわかった。
「ほほぉ……」
「紅くも無いですし、等級が付けられるようなものでもありませんがね。まあ、一般的なホシというとこちらでしょう。この程度のものでしたら、割とこの辺に転がっていますよ」
簪屋は手の中の石を助手に手渡すと、今度は肩から下げた鞄の中から耐熱シィトを何枚か取り出した。それを衣琉と助手に手渡すと、ばさりとその耐熱シィトを広げた。
「そろそろ、あの七曜の星の右下……メラクという星なんですがね。アレが中央区の時計塔に隠れます。ホシが降ってくるのは大体その前後なんですよ」
衣琉は簪屋の指差した空を見上げた。柄杓の形をした七曜の星。ポラリスから数えて七曜の二番目にあるメラクは、確か二等星だっただろうか。その星は、杜京の中心街に聳え立つ時計塔に今にも隠れようとしていた。
「……来ましたね」
不意に簪屋がそう呟くと、手にしていた耐熱シィトをぴんと張って軌道エレヴェエタの上の方を見上げた。衣琉も慌てて同じようにシィトを広げて待機する。やがて、夜空に紅い流星が幾つも流れ、ぱち、ぱちんと弾けるような音が軌道エレヴェエタに響いた。
見えた。紅く光る何かが軌道エレヴェエタを這う鉄のパイプ沿いに、時々ぶつかって弾けながら落ちてくる。それはまるで衣琉の目の中に落ちてきそうな勢いで、思わず衣琉は目を瞑った。直後、シィトを持っている手にぽす、ぽすと振動が伝わった。
そっと目を開くと、シィトの中には蒲公英の綿毛程の大きさはある黒ずんだ石が2〜3、転がっていた。しかし、軌道エレヴェエタ沿いにまた、あの弾けるような音が聞こえてくる。衣琉は不意に、その石を素手で掴もうとした。
「触れないで! 落ちてきた直後のホシは物凄く熱いです!」
簪屋は慌てて、耐熱手袋を付けた手で衣琉のシィトの中にある石を掴み取る。衣琉は空になったシィトをまた広げて、第二弾に備えた。
結局その後、石は4〜5回に渡って落ちてきた。回収できたものは20個以上はあるだろうか。簪屋は満足そうな顔で、回収できた石を巾着袋の中に入れていった。
「研磨してみないと等級はわかりませんが、今日はなかなか豊作です。やはり人手があると違いますね」
そう言って簪屋は、取りこぼして砕けた石の欠片を手にした。それは確かに、光る内包物を含み紅く輝いていた。
「これが……紅いメテオライト」
「学者さんがたはそう言いますね。所謂、【紅いホシ】です。これは割れてるし等級も然程では無いですが、紅いのは希少価値があるのでこれも回収しましょう」
「ふむ。そういったものを粉末にして使ったのがあの簪って事ですかね」
「そうですね……あ、そうだ」
簪屋は思い出したように、鞄の中から綺麗に包装された二つの包みを取り出し、衣琉と助手に手渡した。
「頼まれていたものです。いやぁ、いつもと違う素材と加工方法だったので苦労しましたよ」
包みを開けると、中からは先日助手がつけていたものと同じ意匠の簪が入っていた。助手は、驚いたように目を見開いて衣琉の方に向き直る。
「……本当にお揃いにしたんですか」
「ああ、うん。まぁね」
「しかし、本当にそれで良かったんですか? 学者さんなら、ホシのままのほうが研究材料としても良かったのでは?」
「いやぁ、メテオライトは確かに興味深いが、私はちと分野違いだからね。私にとっては、この形の方が都合が良いんだ」
そう言うと、衣琉は早速髪を纏めて簪を差し込む。扇型に開いた簪の先端は、樹脂のようなもので固められた紅い粉末で点々と飾られ、その先からビラカンのような金属の小さな板がしゃらしゃらと続いていた。中央にも大きく、丸く紅い飾りがついていて、その片隅は小さな蝶のモチィフで彩られている。扇の両端からは、丸い皹入水晶と紅い硝子玉が繋げられていた。
形は確かに同じなのだが、紅い粉末の飾り部分の艶が違う事に助手は気付いた。以前のものと比べて、少し輝き方が鈍いように思う。その代わり、内包物の量が多くなったのか、色味が強くなっていた。
「粉末を固める素材に、経口摂取しても問題無いものを使ってもらったんだよ。粉末の濃度も上げて貰っている」
「先生から渡すように頼まれた注文書、そんな指示をしてたんですか。でもどうして?」
「君の簪から、あの紅いメテオライトの成分を調べさせて貰ったんだ。昔の画家は、紅い色を出すために辰砂という石を使っていたという話は知ってるかい? 辰砂という石は加熱すると毒の成分を出す。辰砂に限らず、毒の成分を含む顔料は多くてね。だから昔の画家はそれで体を壊す事もあったそうだよ」
衣琉はそう話しながら、助手の髪も結い上げていく。そして彼女の手から簪を取ると、自分と同じように結ったその髪に簪を差し込んだ。
「え、早い」
予想外に手早いその手付きに驚く助手を尻目に、衣琉は話を続ける。
「ただ、毒というものは使い様だ。その紅いメテオライトを調べてみると、その内包物に麻酔・鎮痛作用のある成分がある事がわかった。これは使えると思ってね!」
「……まさか」
話を聞いていた助手は、脳内である結論に至り青ざめた。しかし、衣琉は意に介する様子もない。
「そう! そのまさかだ! 次の地上調査には必ずその簪をつけてくる様に! これさえあれば、地上で何かあった時もその場で簡単なオペができるぞ!!」
「いいいいいいやあああああああああああぁぁぁぁぁぁ!!!」
絶叫した助手を見て、衣琉は楽しそうに笑うばかりだった。そもそも、地上でオペをするような事態は相当まずい状況であるし、簡単なオペというがそれはもう絶望的な処置では無いだろうか。
「じゃあ、揃いでって、つまり私に地上調査に同行しろってことじゃないですか……しかも、先生に何かあった時処置をするのが私ってことじゃないですか……」
「ご明察だ! 流石は助手君! いざという時は私の命は君に任せたぞ!」
「流石じゃないですよ、もう……」
助手は呆れ果てて、がっくりと肩を落とす。しかし、そうだ。この人はそういう人だった。そういう衣琉だからこそ、助手は敬愛しているし尊敬しているし、自ら志願して助手となったのだ。
「次の地上調査が楽しみだな、助手君! まだまだ地上は冒険し足りないぞ!」
楽しそうに笑う衣琉を、半ば諦めた様な表情で助手は眺めた。二人の髪には簪に飾られた紅い丸薬が、きらりと輝いていた。
※この物語はフィクションです。実際の簪の紅い飾りには作中のような効能はありません。空想の一助としてお楽しみくださいませ。
終
- ≪前へ
- 紅いホシの物語 TOP
- 次へ≫