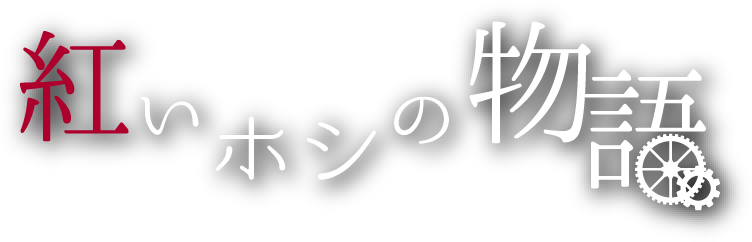星降 ノ花櫛
2
「……で、憂さ晴らしにここに来たって訳ですか、センセ」
「まあ、そういう事になりますね」
色街に来ておきながら、ただごろごろと不貞寝している小説家は、気怠げな声でそう答えた。ただ件の櫛を手の中で弄んで、ぼんやりと眺めている。和は、この廓の一番の遊女というわけではないが、それでもそこそこに名のある女である。その和の前でこの様な態度を取られるのは、やや彼女の矜持を傷付けたが、そこは遊郭の女であるので何食わぬ顔してまた三味線を爪弾き始めた。
そもそも、この非水という筆名の小説家は、和の太客ではあるのだが、一度も和に触れたことがない。廓に来てもこうして寝ているか、酒を飲んでいるか、和の箏や三味線に耳を傾けるぐらいだ。それなら和以外の女でも良さそうなものだが、非水は初会から変わる事なく和の元に通い続けた。
「今日も、共寝はなさらないのですか」
和は三味線を弾く手を止めて、非水に声を掛ける。非水は櫛を弄ぶ手は止めずに、自嘲する様に口の端を歪めた。
「いいじゃないですか、楽な客でしょう?」
「楽過ぎても、張り合いがないってもんですよ。もう弾ける曲は一通り弾いてしまいましたしね」
「わざわざ、そんな事までしなくていいんですよ。ただ、そこにいてくれるだけでいいんだ……いてくれるだけで」
そう言ってこちらを見つめる非水の目は、和を見ている様で見ていない。和は経験から、それが愛しい女を見ている時の男の目であると知っている。しかし、非水の目線の先にいるのは、恐らく和ではなく、和によく似た誰かであるのだろう。和はそれを、敢えて口には出さない。ただ、曖昧に笑ってみせた。
ふと、和は非水の手元の櫛を注視した。その花櫛の中央に据えられた石に、見覚えがあった。
「ちょいと、失礼しますね」
和は、非水の手からその櫛を摘みとる。やはり、と和は思った。
「これ、巷で流行っている【紅いホシ】ですよ」
「紅いホシ?」
「馴染みの簪屋が取り扱っているんです。私も一度この石の簪を買ったんですが……無くしちまいまして。なんでも、十六夜の夜にだけ軌道エレヴェエタ沿いに落ちてくるというホシで、紅いものは希少価値が高いんだそうです。しかもこれ、相当等級の良いものですよ」
「へえ……」
男は興味無さそうに生返事を返したが、和は妙な違和感を感じていた。別れた男に嫌味を言うためだけに贈るには、この櫛は良いもの過ぎる。
「そんなに良いものなら、貴女に差し上げますよ。簪を無くされたんでしょう? 使いもしない私が持っているよりは、貴女の様な女性に使ってもらった方が櫛も本望でしょう。そうだ、それがいい」
そう言って男は起き上がったが、和はそんな非水を冷ややかな目で見つめて櫛をその手に投げ返した。
「勘弁してくださいな。そんな曰く付きの櫛、喜んで受け取るとでもお思いですか?」
「だって、私が持っていたってしようのないものですよ」
「それこそ、この櫛を使ってひとつお話でも書いてみたらいかがです? 芸の肥やしにしてしまうのも、ひとつの手だと思いますよ?」
「……色恋の話を書くのは、どうにも苦手でね」
非水は苦笑いして、櫛を懐に仕舞い込んだ。枕元の酒を手酌で煽り、ひとつ、深く溜息を付く。
「紅(くれない)の話を書こうかと思っているんですよ」
紅。その名前に、和は内心で動揺した。この杜京で満月の夜にだけ現れる無差別殺人鬼。紅に恐怖して満月の夜は客足が遠のく程であったがしかし、実は和は紅に邂逅した事がある。そして自分がその殺人鬼に心奪われていることに、和は薄々気付いていた。
「何か、ありませんかね。紅についての面白い噂とか」
そんな和の心中を知ってか知らずか、非水はそんな話題を和に投げかけた。
「……それなら、それこそその【紅いホシ】ですよ」
「へえ?」
「紅は、その髪に紅いホシの簪を付けているという噂があるんです。紅いホシが人気なのもそれが理由の一因らしいですよ」
「なんでまた、殺人鬼が身につけているものが人気に?」
「杜京の中央軍が出している人相書き、見たことあるでしょう? 相当な色男という【噂】じゃないですか」
「ははぁ……なるほど」
非水は部屋の隅に置いていた鞄を手元に手繰り寄せ、万年筆と手帳を出して走り書きを始めた。和の側にいながらこんなことを始めるのも珍しくない姿だった。
「ではなぜ、紅はその簪を付けているのか……ってところが、気になりますね」
非水の言葉に、和は目に動揺の色を浮かべた。幸いにして、非水は手元の手帳を見ていたので、和の様子に気付いてはいなかった。
「……会ったんです」
和の口から漏れた吐息のような言葉に、非水は手を止めて和の方を顧みた。和の紅を差したその唇の色が、まるであのホシの色のようだと非水は思った。
「私が無くした簪……それが今、紅の手元にあるんですよ」
和は無意識に、自分の口元に手を寄せていた。それを見た非水は、何かを察したようだった。
「いやはや、もしや私の恋敵は巷を騒がせる殺人鬼ですかね? ……これは手強いな」
「あら、恋敵だなんて。心にもないことを仰いますのね」
和と非水は、同時にふ、と笑った。
夜は静かに更けてゆく。ひとつ、またひとつと消える灯りと共に、他の部屋から漏れ聞こえ始める嬌声。和は手慰みにまた何か弾こうかと撥を手にしたところで、先ほどの違和感の正体を思い出した。
「センセ……櫛を贈るのは縁起が悪いと言われてますけどね。それだけでもないんですよ?」
「へえ?」
「確かに櫛は、【苦】と【死】が入っています。でもそれを逆手に取って、幸せも苦労も多い人生を、死ぬまで共に……という意味で、求婚の時に男性から贈ることもあるんですよ」
「だが、それは違うだろう。私はもう……」
「もうひとつ。櫛は女性が髪につけるもの。魂に近い頭部につけていることで、櫛には魂の一部が宿るとされているんです」
非水の動きが止まり、その目線を和のほうに向ける。無意識にか、非水の手は懐のあたりに添えられていた。ちょうどそれは、先程櫛をしまい込んだあたりだった。
「道を分つ想い人へ……せめて魂だけでも連れていって欲しいと。そんな意味もあるんですよ」
和は、非水の手にそっと自分の手を重ねる。非水の手が震えているのがわかった。そのまま非水は、懐からまた先程の櫛を取り出した。
「ははは……ありがとう。優しい解釈だ……」
声を震わせながらも、非水は気丈にそう呟いた。
和は非水の手からまた、その櫛をつまみ取った。先程和はもうひとつの違和感を感じていた。あの簪屋が作った櫛にしては少し作りが甘いというか、一度解体した様な痕跡があった。
「ああ、やっぱり。ここを見てくださいまし」
和が指差したのは、ホシと金属の花弁の繋ぎ目。ホシは丸く削られ、中央に開けた穴に天糸を通して土台に繋ぎ止められているのだが、その天糸に混じって黒く細いものが巻き込まれていた。
「……髪」
「絶縁したい相手などに、誰がこんな小細工までして髪など仕込むでしょう?」
非水の手はわなわなと震え、されどもその震える手でそっと、櫛を握りしめた。そのまま非水は和の膝に頭を預けしばし動かなかったが、しばらくして小刻みに震え始めた肩は、やがて嗚咽と共に激しく上下に揺れていた。
そこから先は和も特に何を話すでもなく、ただ優しく非水の癖のある髪を撫で続けた。行燈の灯りが仄かに揺れる。もうしばらく経てば消えてしまうかもしれない。それなら、それで。
後にも先にも、非水が和に触れたのは、たった一度この時だけであった。
終
- ≪前へ
- 紅いホシの物語 TOP
- 次へ≫